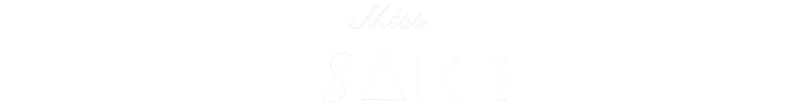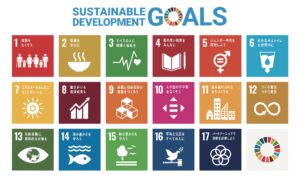皆様、こんにちは。
2023 Miss SAKE 宮城 千田瑞穂です。
5月18日(土)19日(日)、一泊二日の「2024 Miss SAKE ナデシコプログラム 宮城県特別講義」に2024 Miss SAKE ファイナリスト、Miss SAKE OGで参加させていただきましたのでご報告させていただきます。
今回の特別講義の開催地は、私の故郷である宮城県でした。
宮城県出身でありながら知らないことがたくさんあり、宮城県の魅力を再発見し、より素晴らしさを掘り下げることができた2日間でございました。
今回は、1日目の様子をご報告させていただきます。
<講義内容>5月18日(土)
1 株式会社佐浦 本社蔵見学・鹽竈神社正式団体参拝
株式会社佐浦 代表取締役 社長 佐浦弘一様 https://www.urakasumi.com/
2 株式会社和がき 漁場見学
株式会社和がき 代表 阿部年巳様 https://wagaki-miyagi.jp/
3.プランニングルームMP代表/宮城県6次産業化プランナー/みやぎグリーンツーリズムアドバイザー 早坂久美様
4. 宿泊先:未来学舎KIBOTCHA/キボッチャ https://kibotcha.com/
1 千年を超す長い歴史の息づくまち塩釜〜浦霞醸造元 株式会社佐浦様蔵見学・鹽竈神社 志波彦神社 正式団体参拝〜
塩釜の浦は、古くから景勝地としても知られ、いにしえの京都の貴族達の憧れの地であり、その美しい風情が多くの歌に詠まれています。
国指定重要文化財に指定された鹽竈神社は千年以上の歴史を有しており、今年で創業300年を迎えられた佐浦様ですが、江戸時代後半には鹽竈神社の御神酒酒屋となってお酒を醸し、現在に至ります。
初めにマーケティング本部 企画部 冨谷圭輔様より会社のご紹介をしていただき、前半は、2チームに分かれ、蔵見学をしました。
仕込みをしているタイミングで伺うことができたので、実際にお酒造りをされている様子を見ながら蔵の中を見学してまいりました。仕込み中ということは大変繊細な時期です。そのような中、私たちを受け入れてくださったことに、心から感謝申し上げます。副杜氏である山田様が丁寧に説明をしてくださいました。
原料米はササニシキ・トヨニシキ・まなむすめ・蔵の華・吟のいろはなどを使われているそうです。それぞれのお米に特徴があるので、そのよさを引き出すことができるように時間を計り、浸漬をしているとのことでした。
ササニシキを60%まで磨いた蒸米をいただきました。
蒸しあがったばかりで甑からは蒸気が上がっており、お米の柔らかい香りがします。
「周りは固いけど、中はもちもちする。」
蒸米をいただく機会など滅多にないので、ファイナリスト一人ひとりが大変感動しておりました。
麹室では、乾燥させている麹をいただきました。
麹をいただく機会も滅多にございません。
「小さい。」「かたい。」「甘い。」「甘酒みたいな味がする。」「ポン菓子みたい。」
説明をしていただくだけでも十分に有難いのですが、麹を視覚、触覚、味覚で感じながら、蓋麹や箱麹のお話、麹室の温度のお話、泊まり込みで作業をされるお話、蔵に持ち込んではならない菌のお話などをしていただきました。
皆様、蔵見学の前に納豆や柑橘類、ヨーグルトなどを食べてはならないことはご存知でしょうか。
日本酒を造るのに欠かせない麹菌。蔵では菌の力を借りて、繊細に日本酒造りを行っております。そこに納豆菌を持ち込んでしまうと、日本酒造りに重要な麹菌に悪い影響を与え、味が全く変わってしまうのです。納豆菌は菌の中でも強く、一度蔵に住み着いてしまうと除去が不可能とさえ言われております。柑橘類も麹菌に悪い影響を与えます。乳酸菌は、醪に悪い影響を与えると言われております。
蔵で見学をさせていただく際には、マナーとしてこのような基礎知識を身につけておくことも大切なことなのです。
外へ行くと、大きな木桶がございました。
日光で消毒されているところでした。
佐浦様は、ステンレスのタンクでもお酒造りをされておりますが、南部杜氏流の伝統的な製法でのお酒づくりも大切にされております。
南部杜氏の至宝である平野佐五郎様、またその甥で半世紀以上に渡り佐浦様のお酒造りを支えてきた平野重一様。
丁寧なお酒造りによって各種鑑評会で数々の受賞歴を有し、お酒造りの歴史に名を刻みました。
そんな平野様より指導を受けた木桶の仕込みやメンテナンスを、今でも大事にされています。
木桶で仕込むと、お酒に木の香りがほのかに移り、コクが出るそうです。
しかしながら、近年では、昔ながらの木の道具を取り扱う業者が少なくなってきているようです。
竹ささら(竹で作ったブラシ)で洗ったり、日光で消毒されたり、柿渋で防虫対策をしたり、今でも木桶を丁寧に扱っており、受け継いだ伝統をどれだけ大切にされているのか触れることができた瞬間でした。
東日本大震災についてのお話もありました。
蔵の壁にはどこまで浸水したかが分かるように線が引いてあります。
当時の冷蔵貯蔵庫のお写真も見せていただきました。
3万本ほどお酒が破損・被災してしまったそうです。
東日本大震災をきっかけにステンレスのタンクを取り入れたそうですが、震災対策としてタンクの足を5本にするなど、少しでも被害を最小限にできるよう工夫しているとのことでした。
仕込蔵では、仕込み中の酒母とタンクを見せていただきました。
泡の大きさの違いを見たり香りを体感させていただいたりしました。
仕込み歌は南部杜氏流であることや女性の杜氏がいらっしゃることを教えていただきました。
搾りについては、袋吊りや槽、ヤブタ式等、香りが繊細な大吟醸と普通酒では、搾り方が異なることを教えていただきました。
さて、こちらは佐浦家の家紋です。真ん中にあるものは何でしょう。
正解は、丁字(チョウジ)です。英語でClove(クローブ)とも言います。
丁字は香辛料です。
佐浦家の家紋は「丸に違い丁字」。
珍しい家紋にファイナリスト達が驚いておりました。
蔵見学後は、代表取締役社長 佐浦弘一様(十三代目蔵元)より、銘柄「浦霞」についてお話をいただきました。
しおがまの浦の松風霞むなり 八十島かけて春や立つらむ
源実朝(1192-1219年)「金魂集」より
「浦霞」の酒銘は、この塩釜の浦に春の訪れを告げる穏やかな風情を詠んだ歌から命名されました。銘柄「浦霞」には、塩釜の浦に霞みがかった優しく美しい景色が表現されており、ほのぼのとした春の風景が浮かんでくるような味わいを目指して醸されています。
お酒造りで特に意識されていることは、地域性へこだわることや最高品質を追求することだそうです。
佐浦様は、地元産原料を大切にされております。酒造好適米は蔵の華・吟のいろは、一般米は、トヨニシキ・まなむすめ・ササニシキなどを使用おりますが、全使用量のなんと90%が地元米なのだそうです。
また、最高品質を追求するために欠かせないのが優れた杜氏の存在。先ほども蔵見学のところで触れましたが、佐浦様は南部杜氏流の丁寧なお酒造りを大切にされており、平野佐五郎様・平野重一様の心や技を今でも受け継いでらっしゃいます。
南部杜氏自醸清酒鑑評会では7回の首席受賞、103回中67回の優等賞受賞、全国新酒鑑評会では金賞を38回受賞するなど、全国でもトップクラスの成績を収めております。
飲み比べでは、次の6種類のお酒がご用意されておりました。
・純米吟醸 浦霞禅
・純米吟醸 浦霞No.12
・純米吟醸 浦霞 寒風沢
・浦霞 No.12スパークリング シルバーラベル
・エクストラ大吟醸 浦霞
・純米原酒につけた浦霞の梅酒
佐浦様の説明に合わせて、一つひとつじっくりと味わいました。
「純米吟醸」と一口にいっても、色や香り、口当たりや味わいが全く異なります。
講義後、浦霞ギャラリーにてファイナリストたちが気になるお酒や好きなお酒を各々購入しました。
私は、「純米大吟醸 浦霞No.12」を購入しました。
全国へ頒布された「きょうかい12号酵母」、実は昭和40年に浦霞の吟醸醪より分離されたもので発祥蔵は佐浦様なのです。
皆様ご存知でしたか。
昼食後は、佐浦様に同行いただき、鹽竈神社・志波彦神社へ正式団体参拝をしに伺いました。
こちらは、普段、正式参拝は皇族の方のみが行うことのできる場所です。
そのような場所に我々Miss SAKEが正式参拝させていただけたことに心より感謝申し上げます。
初めに志波彦神社へ団体参拝させていただきました。
志波彦神社は、農業守護・国土開発・殖産の神である志波彦神(しわひこのかみ)が祀られており、
平安時代の「延喜式神名帳」(政府の神社台帳)に、陸奥国百座中の「名神大社」として記載されております。
続いて、鹽竈神社です。
鹽竈神社は、これまで自身で参拝をしに来ることは何度かあったのですが、権宮司様よりこの度丁寧に歴史や神様について教えていただき、より威厳さを感じ、身が引き締まる思いで参拝をさせていただきました。
- Screenshot
- Screenshot
鹽竈神社は、別宮に塩業や漁業の神である鹽土老翁神(しほつちおぢのかみ)・左宮に勝負の神である武甕槌神(たけみかづちのかみ)・右宮に経津主神(ふつぬしのかみ)が祀られております。
鹽竈神社での正式参拝では、まず別宮から参拝するのが正しい順番だそうです。
この別宮にて、神楽を拝見いたしました。
荘厳な中、巫女が鈴の音に合わせて神楽を舞っている姿は大変美しく、思わず息をのんで見入ってしまいました。
そこでは、まるで日常とは違う時の流れを感じ、今でも忘れることができません。
神楽の後、別宮の奥へ通していただき、団体参拝をしました。
海の守護神である鹽土老翁神は、産みの神、安産守護の神とも云われております。
美智子上皇后陛下のお母さまも、美智子様がご懐妊された時は、鹽竈神社に腹帯を求めたそうです。
2024 Miss SAKEファイナリストの中にも、お母様がこちらへ参拝したことで授かったのだという方がおりました。
左宮、右宮では、私はMiss SAKEの御礼参りをさせていただきました。
実は一年前、佐浦様へ蔵見学をさせていただいた後、Miss SAKE最終選考会を控えていた私は、こちらに参拝をしに来ていたのです。
地域活動貢献賞に選出いただいたことを報告し、感謝の気持ちをお伝えしました。
最後に、本宮へ続く202段の階段へ行きました。
昔はこの階段の下に舟をつけていたそうです。
階段の上から下を眺めてみると、もの凄い氣を感じました。
毎年7月に開催される「塩竈みなと祭」では、御神輿を担ぎ、この階段を登られるそうです。
気が付くと、あっという間に時間が経っておりました。
塩竈のまちの深い歴史や文化を肌で感じることができ、かけがえのない時間となりました。
私たちの活動が一人でも多くの方にとって日本酒をはじめ、日本の伝統文化の魅力に触れるきっかけとなりますよう、引き続き誠心誠意努めてまいります。
佐浦様、権宮司 大瀧様、鹽竈神社・志波彦神社の皆様、この度は、貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。
2 牡蠣の成長を見守るホタテ貝〜株式会社和がき 漁場見学〜
鹽竈神社の後は、日本三景の一つである松島へ移動しました。
この度、大変有り難いことに、松島湾で種牡蠣を採取し、全国の牡蠣産地に出荷しておられる和がき様で漁場見学をさせていただきました。
さて、皆様は牡蠣とホタテの関係をご存知ですか。
恥ずかしながら、私は牡蠣を食べることは大好きなのですが、どのように育てられているかまでは知りませんでした。
到着すると、3チームに分かれ、私たちのチームは初めにホタテ貝の殻を見に行きました。
なぜ牡蠣の養殖なのにホタテが関係あるのでしょうか。
私も最初は頭の中が「?」で、牡蠣とホタテが繋がりませんでした。
毎年夏に孵化した牡蠣の赤ちゃんは、2週間ほど海中を漂うそうです。そして、海中の岩などに付着するのですが、その岩の代わりに赤ちゃんをキャッチしてくれるのがホタテの殻なのだそうです。付着した牡蠣の幼生を丁寧に育てていきます。
実は、ホタテは牡蠣の成長を陰ながら支えているのです。
これを手作業で何セットも作っているというのです。
私たちもホタテの殻の穴開けに挑戦してみました。
鎌を使うのですが、結構力がいる反面、ヒビも入りやすく割れてしまう人もおり、難しかったです。
ご指導いただき、何とか穴を開けることができました。
次に漁船へ乗って実際に牡蠣を養殖してらっしゃるところを見学しに行きました。
プランクトンは海面から5mほどが豊富で、海の底の方よりも上の方が育ちやすいそうです。
このように間を少しバラし、隙間をあけることによって、栄養が行き渡りやすくなり、育つスピードが上がるそうです。
一枚に50個ほど着くそうですが、全て順調に育つわけではなく、中には死滅するものもあるので実際に捕れるのは20個ほどとのことでした。
ちなみにこの綱一本分で30kgほどあるそうです。
海によって育て方が違うようで、岩手の方の海だと、一枚に5個ずつ裏表につけ、1個1個育てるというところもあるそうです。
漁場見学の後は、株式会社和がき様、プランニングルームMP代表宮城県6次産業化プランナー早坂久美様のご協力のもと、宮城の日本酒と、海の幸を存分に味わいました。
ファイナリスト全員でBBQの準備に取り掛かりました。
生牡蠣、焼き牡蠣、蒸し牡蠣、牡蠣のアヒージョ、パスタ、、、
「今日は牡蠣が、2トンあるから」と、たくさん牡蠣をいただきました。
こんなにも新鮮で美味しい牡蠣をお腹が膨れるほどいただく機会は滅多にございません。
味の組み合わせも様々試し、楽しみました。
また、牡蠣だけではなく、塩竈の魚市場より弊社大西代表が新鮮な鮪を買い付けてくださり、一緒に楽しみました。人生で初めて鮪の心臓を初めていただきました。カマも美味しくいただきました。
海の幸には、やはり日本酒が合います。
佐浦様の「純米大吟醸 浦霞 No.12」「浦霞 純米生酒」「浦霞 純米酒」、平孝酒造様の「日高見 芳醇辛口純米吟醸 弥助」「日高見 超辛口純米酒」をお食事に合わせていただきました。
牡蠣をいただきながら、地球温暖化によって海水温が上昇していることや、海の生態系への影響についてお話を伺うことができました。
近年、海水温上昇に伴い、かつては捕れていた魚が捕れなくなり、反対にあたたかいところでしか捕れなかった魚が捕れるようになってきているそうです。
この状況を見過ごすことはできず、危惧しているとのことでした。
温暖化の原因は人間が出す二酸化炭素であるということは分かっています。
自分事として捉え、今後どのような手を打つか考えていかないと、これまでの当たり前が当たり前でなくなってしまう未来がそう遠くはないのではないかと考えてしまいました。
最後は仙台名物である牛タンをいただき、マシュマロで締めました。
世界三大漁場の三陸の海が育む宮城の牡蠣。
この度は、どのように育て、水揚げされるのかを現地へ足を運び、学ぶことができました。
この学びをしっかりと今後の活動に生かしてまいります。
阿部様をはじめ、株式会社和がきの皆様、プランニングルームMP代表宮城県6次産業化プランナー早坂様、
このような貴重な機会をいただけましたことに心より御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。
3 未来学舎 KIBOTCHA/キボッチャ
希望、防災、未来(フューチャー)。
KIBOTCHAという名前は、この3つを組み合わせた造語で「これからの時代を支える子どもたちの未来に命の大切さを伝えたい」という想いが込められています。
東日本大震災により津波被害を受けた旧・野蒜小学校跡地を再利用した施設で、宿泊利用の他、入浴のみの利用や食事、体験学習等、様々な関わり方ができます。
施設の2階にはアスレチックがありました。
よく見ると津波のイラストが書かれており、遊びながら防災意識を高める工夫が見られました。
また、同じ階に語り部ルームや東日本大震災についての資料が展示されているお部屋もございました。
大浴場は、古来より親しまれている槇の木を使用されており、木の香りやぬくもりに大変癒されました。
今回は利用しなかったのですが、屋外でBBQやグランピングもできるようです。
ファイナリストと「またゆっくり来たいね。」と、話をしました。
翌日の朝食は、野蒜の食材を使ったものを美味しくいただきました。
1日目、大変豪華なプログラムでたくさんのことを吸収いたしました。
翌日、疲れを引きずらず、リセットできたのはキボッチャ様にてしっかり羽を休めることができたからなのではないかと思います。
大変快適に過ごさせていただきました。
東日本大震災での学びを未来へ繋ぐ取組をされていることに大変心が動かされました。
またゆっくり足を運び、体験活動等に自ら参加してみたいという思いをもちました。
この度は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
2023 Miss SAKE 宮城 千田瑞穂