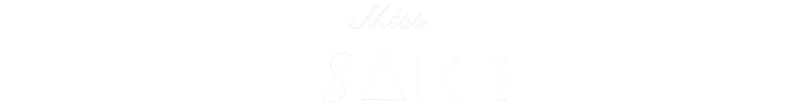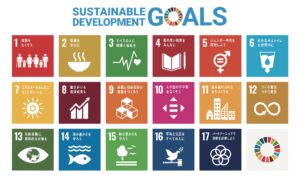【ナデシコプログラム 第13回】
皆さま、こんにちは。2024 Miss SAKE 東京 高島桃子です。
5月11日(土)の第13回のナデシコプログラムに参加してまいりましたので、ご報告させていただきます。
【講義内容】
①小津和紙高木清様「和紙漉き体験」
②江戸切子の店華硝取締役 熊倉千砂都様「江戸切子体験」
【各講義の感想】
①小津和紙高木清様「和紙漉き体験」
小津和紙は江戸時代に創業した和紙の専門店です。日本各地の和紙を取り揃えた店舗をはじめ、史料館やギャラリー、和紙づくりを体験できる工房があります。
店舗には、書道用紙、工芸用和紙、手漉き和紙など様々な和紙製品が置いてあります。色やサイズも様々なので、用途に合わせて自分にピッタリの和紙を購入することができます。和柄の透かし模様が入ったティッシュやトイレットペーパーなどもあります。
史料館では、369年の歴史を持つ小津和紙の歴史について学ぶことができ、和紙を使用した当時の古文書や帳簿の他に千両箱も見ることもできます。また、和紙は1000年以上保存できるとも言われ、その綺麗な保存状態は圧巻です。
体験工房ではなんと自分でオリジナルの手漉き和紙を作ることができ、「楮(こうぞ)」という木の皮の繊維を1本1本にほぐした繊維を水に混ぜた原料から、昔ながらの道具を使って紙を漉き、乾燥させて和紙を作る、という工程を1時間で学びながら体験できます。
色楮や金銀箔、様々な和紙などを使ってデザインすることもできるので、世界に一枚だけの和紙をつくることができます。
今回 プログラムで、和紙漉きの体験をさせていただきました。
教えてくださったのは、指導員の高木様。とても明るくテンポよくわかりやすく教えていただきました。元々商社部門にいて、こちらの和紙部門に来て10年、指導は4年。目の前でお客様が楽しんでくれたり、喜んでくれる姿を見ることがやりがいだそうです!
楮という木の皮の内側から取った繊維で和紙を作ります。水槽に沈殿している和紙の素を浮き上がらせます。防水エプロンを貸していただけるので手ぶらで大丈夫でした。
それではいよいよ和紙漉き体験スタート!
①下準備
棒で楮・水・ネリで出来た紙料をかき混ぜて攪拌し、和紙を漉く準備をします。ネリが含まれているので結構重労働です。
②紙漉き
次は紙漉きの作業になります。簀桁(すげた)を用い、ベースとなる紙を作ります。まずは紙料を軽く掬って捨てるのを2~3回行います。続いて紙料を多めに掬い、それを木枠内でシャカシャカ揺らし、水が完全になくなる前に捨てます。それを数回行ったらもう一度紙料を軽く掬って捨て、和紙の完成です。
③脱水
簀から外した和紙をフレームごと隣の台に移し、脱水機で水分を取ります。脱水機は、実は掃除機。少々ビックリでした。
④乾燥
水分を取ったら、60℃くらいに温まった鉄板に和紙を貼付け、刷毛で和紙の中の空気を抜きます。例えるならスマートフォンの画面にフィルムを貼った時に出来る気泡を外に押し出すような感じです。
⑤完成
10分くらいで乾燥し、世界に一枚だけのあなたオリジナルの和紙が完成します。更にお好みで小津和紙さんの落款を押すこともできました。
この紙漉き体験は10年前ぐらいから行っていらっしゃるという。その目的は、お客様に和紙に興味を持っていただくためとのことだそうです。体験されたお客様は3歳から105歳までとバラエティーに富んでおり、半分は外国の方だそう。最近は修学旅行や大学のサークル、主婦のグループも増えており、手軽な日本文化体験として外資系企業の接待にも使われているそうです。また、体験者の中には和紙作りのおもしろさに気づき、プロの道を選び、和紙の産地で修業している方もいるといいます。
和紙に興味を持たれた方、日本の文化に触れてみたい方には、都内の便利な場所にあるので利用しやすいです。インバウンドが注目するのももっともな、価値ある施設だと感じました。
②江戸切子の店華硝取締役 熊倉千砂都様「江戸切子作成体験」
洞爺湖サミット贈呈品をはじめとする国賓の贈呈品を賜る、江戸切子の工房の直営店。独自の紋様と繊細なカットの技は海外でも人気があります。体験スペースも併設。本場日本橋で本物の江戸切子の文化に触れることのできる店舗です。
江戸切子の特徴は、カットと磨きの技術にあり、華硝ではすべての行程を手作業で行っています。硝子に刻まれる模様は、矢来、麻の葉、菊など古典柄からモダンな柄まで50種類ほど。グラインダーで削った後、断面を丁寧に磨くことで、輝きが生まれるそうです。「手間がかかる作業なので、いまでは磨きを薬品で行うところも多くなっていますが、うちでは昔ながらの製法を守り続けています」。手磨きにより生まれる独特の光沢、透明感が華硝の持ち味。色は紅色、瑠璃色、葡萄色といった伝統色のほかに、オリジナルで水色も展開しています。
日本橋本町にある店舗では、この歴史ある江戸切子づくりを体験することができます。まずは赤、青色から好きな色をチョイス。初めての方は、作業中にカットした模様が見えやすい赤やぶどう色がおすすめだそうです。次に見本を見て、マーカーで下書きに沿って硝子の上に機械で模様をカット。工房の職人は50種類もの金属歯を駆使して制作するそうです。今回の体験では、1種類の歯で底の部分から削り始めました。実際に削ってみると、繊細な紋様を寸分の狂いもなく仕上げる職人のすごさを感じました。
模様をカットしたら、ペンで描いた下書きをスチールウールで落として完成です。通常、磨きは薬剤で行うことが多いですが、華硝では昔ながらの手磨きを行っています。それにより、独特な柔らかい色彩が生まれるといいます。わずか1時間ほどで、ぐい飲みを仕上げることができます。自分で削った江戸切子でいただく冷酒の味わいは、きっと格別だろうなと今からとても楽しみです。
この度は貴重な機会を頂き本当にありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。