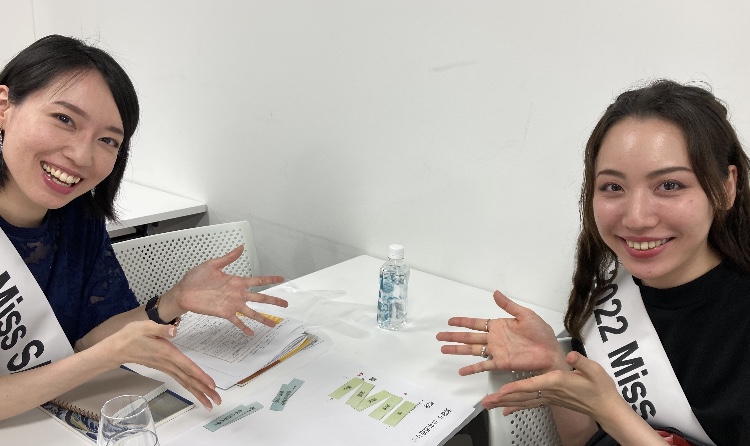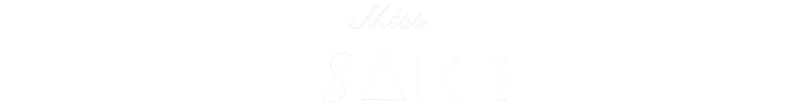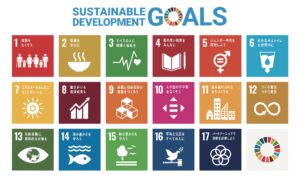皆様こんにちは、2022 Miss SAKE 東京 川上千晶です。
第14回ナデシコプログラムでは、キャプラインワインアカデミー様にてWSET SAKE Level1を受講して参りましたのでご報告させて頂きます。
WSETとは?
まず、本日受講させて頂くWSETという教育機関について。
こちらはロンドンに本部を置く世界最大のワインの教育機関です。
ワイン商組合『Vintners Company』により1969年に創設され、現在では世界70ヶ国でWSETの教育組織が運営、今では年間約95000人が認定試験を受けるなど、国際的に認められた認定資格になっています。
WSET:https://www.wsetglobal.com/jp/japanese-qualifications/
WSETでの日本酒資格について
ワインの教育機関であるWSETには当初、日本酒のコースはありませんでした。
しかし第7回ナデシコプログラムでご講義頂きました、株式会社コーポ・サチ代表取締役社長の平出淑恵様の働きかけや、沢山の方々のご尽力により、この世界的な教育期間・WSETに日本酒のプログラムが組み込まれるようになりました。
「日本酒を世界に発信したい」「日本酒を世界的な酒にしたい」
という沢山の方々の熱い想い、そして多大なるご尽力の上でこのような学びの機会を頂けるということに感謝の気持ちを持ち、日本酒のアンバサダーとして日本酒をあまりご存知でない方にも分かりやすくお伝えしていけるようご講義を通し、学ばせて頂きました。
日本酒の製造工程
日本酒がなぜ「日本」酒と言われるのか。それは日本酒の原材料である米はもちろん、その製造工程に日本独自の奥深い魅力が隠されているからです。
日本酒の製造工程は大きく以下の三つに分けられます。
一、発酵
二、上槽(じょうそう)
三、瓶詰め
この過程の間に、「醸造アルコールの添加」や「加水」、「火入れ」が任意で行われ、その工程を加えるか否かによって、日本酒のスタイルや味わいが異なります。
一、発酵
日本酒の原材料は蒸し米、水、麹、酵母です。
まず、優良な酵母を培養するため、主発酵の前に『酒母』(酛:もと)を造ります。
酒母が出来上がったら主発酵のためのもろみに移るため、より大きなタンクに酒母・水・蒸米・麹が段階的に投入されます。
この時、タンクの中では『並行複発酵』という日本酒の醸造過程にのみ見られる珍しい発酵が行われています。
並行複発酵とは…お米に含まれるデンプンの糖を酵母が摂取してアルコールが生成されますが、その前にデンプンを糖に分解する必要があります。その役割を担うのが、麹に含まれる酵素です。
麹に含まれる酵素がデンプンを糖に分解し、その糖を酵母が摂取してアルコールが生成される。このように「糖化」と「発酵」が同時に行われるのが『並行複発酵』です。
この過程を同じ醸造酒であるワインやビールと比較してみると、ワインは原材料のブドウに糖が含まれているため、原材料に酵母を加えるだけでアルコールを生成する事ができます(単発酵)。
また、ビールは原材料である麦に含まれるデンプンの糖化とその糖を発酵する工程が別々に行われます(単行複発酵)。
このように、同じ醸造酒でもそれぞれに発酵方法が異なっており、日本酒の『並行複発酵』は世界に類を見ない珍しい発酵方法ということが分かります。そしてこの手法により、日本酒の奥深い味わいが醸し出されているのです。
二、上槽(じょうそう)
発酵が終わると、次にもろみを「濾す」作業を行います。
全ての日本酒は法律によって製造過程で濾さなければならないと定められていますが、この過程で「どれぐらいの細かさに濾さなければならない」と定められているわけではありません。
ここで粗く、米の原型をより残したスタイルの日本酒が「濁り酒」と呼ばれています。粗く濾されていることでお米の旨みやまろみ、独特の喉越しを感じられるお酒に仕上がるのです。
また、上槽する前に任意で「醸造アルコール」をもろみに添加することもあります。ここでも添加するかしないかで、日本酒の味わいやスタイルが異なってきます。
三、瓶詰め
最後に、瓶詰めの工程です。上槽された日本酒は、瓶詰めされる前に大抵の場合「加水」がなされ、約20度のアルコール分が15〜17度に調整されます。また瓶詰めされた後劣化臭を防ぐために「火入れ」処理がされますが、この火入れ処理を行わないお酒を「生酒」と呼びます。火入れをしないため、しぼりたてのフレッシュな味わいを楽しむ事ができますが、品質管理に十分注意する必要があります。
以上のような工程を経て、お米とお水から様々な味わいの日本酒が造り上げられます。
ご紹介した工程はほんの一部ですが、この過程を学ぶだけでも日本独自の発酵方法や工程によって、日本酒が独自の味わいと文化を醸成してきた、という歴史を垣間見ることができます。
またご講義の中で、製造工程やお米の精米〜蒸米までの過程を手を動かして落とし込もう!と、講師の鈴木更紗様よりカードをお配り頂き、過程の復習をグループで行いました。
「読む」「書く」だけでなく、「話す」「手を動かす」といったアプローチをとることでより深く知識を定着させる事が出来るという事を実感いたしました。
テイスティング入門
日本酒の味わいについて今まで、「純米酒だからお米の旨みが強い」や、「吟醸酒だから洗練された味わいと香りがする」など、初めから味わいを多少想像してお酒を味わってきたように思います。
しかし今回のテイスティング入門では「より自分らしい言葉で分かりやすくお酒を伝える」ことを重点的に、「このスタイルのお酒だからこう」と単一的に捉えるのではなく、より多角的にお酒を捉え、表現することを教えて頂きました。
自分の言葉で表現してみよう
テイスティングでは、順番を追ってそのお酒が「どんなキャラクターを持ったお酒なのか?」を一つずつ紐解いていきます。
まずは外観から。
澄んでいるのか、濁っているのか。色は無色透明か、少し黄味がかったレモン色なのか。
出来れば白いテーブルの上で(無ければ白い紙を敷くだけでも色味が分かりやすいです)少しグラスを傾けて観察します
次に香り。
ここで鈴木様から、より伝わりやすい香りの表現方法を教えて頂きました。
それは「自分の経験から近いものを持ってきてそれを更に分解する」といった表現です。
例えば、お酒の香りについて「おばあちゃんの家の香りがする」と咄嗟に感じた場合。
「おばあちゃんの家の香り」はその人にしか分かりません。
そこで「どんな香りがおばあちゃんの家の香り」なのか?を分解してみると、
- お香の香り
- 畳の香り(いぐさの香り)
- お花の香り
といった誰にでもイメージしやすい香りの表現が見えてきます。
果物の香りを感じた場合も、果物、とだけ表現するのではなく、具体的にりんごやバナナ、またはその果物が入ったケーキ等、自分の感じた香りを具体的に変換する練習をしていくと、より相手に伝わる表現が出来る事を教えて頂きました。
最後に味わい。
味わいも先程の香り同様、より具体的な表現をすると伝わりやすくなります。私が個人的に驚いたのは先生の「マスカット」ではなく「マスカットのバブルガムのような甘みとフルーティーさ」といった表現方法です。
他にも「トースト」や「ポン菓子」、「バナナミルク」といった一見日本酒の説明には程遠そうな言葉たちも実際に日本酒からそれらの味わいが感じられ、そのお酒をより具体的に表現する上で非常に有効であると感じました。
「このお酒は吟醸酒だからフルーティーな香りだろう」ではなく、一つ一つのお酒に向き合い、味わいを深く探求する事こそテイスティングの醍醐味の一つだと実感した瞬間でした。
料理と温度管理…多様な日本酒の魅力
日本酒の魅力の一つに「幅広い温度帯で楽しむ事ができる」という点があります。
夏はキリッと冷やした冷酒を楽しみ、冬は熱燗や飛び切り燗で冷えた体を温める…など一年を通して様々なシーンで楽しめるのは日本酒だけ、といっても過言ではないはず。
ご講義の後半ではそんな日本酒の温度による味わいの変化、そして料理との組み合わせについて実習を交えて教えて頂きました。
温度帯による味わいと香りの変化
今回、先程テイスティングさせて頂いた中から純米酒と純米吟醸酒の2種類をお燗にし、その違いをみんなで味わいながら分析しました。
今回は約40度のぬる燗にして二種類の日本酒を味わいました。
お猪口に顔を近づけた瞬間、ふわっと香るお米と乳酸の香り。常温でテイスティングした時と全く異なる香りに驚きながら口にすると、そのまろやかで柔らかい口当たりに再度驚きました。
温度を上げることで「お酒の角が取れた」ような、お酒そのものの表情が柔らかくなった、そんな味わいの変化を感じました。また一般的には吟醸酒は冷やで飲むことが好まれていますが、今回頂いた純米吟醸酒はぬる燗にしてもとても美味しく、お米の柔らかな旨みを感じ、私はぬる燗でまた頂きたいと思う程でした。
お料理と合わせる上で大切な三つのポイント
最後に日本酒と料理の組み合わせについて。
日本酒を楽しむ上で欠かせない要素といえば、一緒に頂くお料理です。
ご講義ではお酒をお料理と組み合わせる上で、次のポイントが重要であると教えて頂きました。
- お料理と日本酒の風味の強さを同じにする
- 甘口のお料理には同じ甘味を持つ日本酒を組み合わせる
- 個人的な好みを尊重す
こちらも実際に様々な味覚と合わせて、お酒の味わいがどう変化するのかを体感を持って学ばせて頂きました。
頂いてみると、甘味には甘口の日本酒が非常によく合う事が分かったり、旨味だけだとあまり合わないと感じた味わいが、旨味+塩味にしてから日本酒を合わせると一気に口中に花開くようなマリアージュが完成したり…とお料理との組み合わせで日本酒の味わいが如何様にも変化する、という事を実感しました。
また、何よりも大切なのは、好ましい味や感覚は人それぞれである、ということ。
先程お燗にした吟醸酒が美味しいと感じたように、一般的にはあまり好まれない合わせ方にも美味しさや楽しさがあるかもしれません。
「このお料理にはこう!」「この日本酒はこう飲むべき!」と頭でっかちになることなく、基本的な知識をしっかりと持ちながら、これからも日本酒の世界を探求していきたいと改めて思いました。
終わりに
見て、触れて、嗅ぎ、味わいながら五感で学んだ日本酒の奥深い世界。
自分が感じた日本酒の魅力を一人でも多くの方に伝えられるよう、本日の学びを生かし、「自分の言葉」で「分かりやすく」これからも伝えて参りたいと思います。
教えて頂きました、鈴木更紗様、本当にありがとうございました!
2022 Miss SAKE 東京 川上千晶