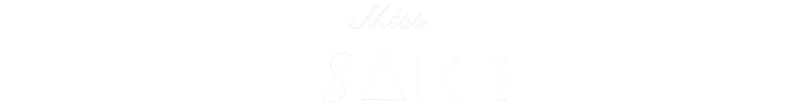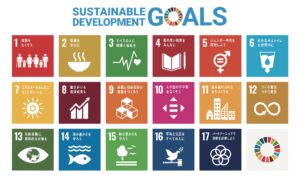皆様こんにちは!
2024 Miss SAKE 京都 津田朋佳です。
第9回ナデシコプログラムの内容についてご報告させていただきます。
◇内容
▪️WSET SAKE Level1
キャプラインワインアカデミー 鈴木 更紗様
◇感想
WSET SAKE Level1を取得するため、キャプラインワインアカデミー 鈴木 更紗様より講義をいただき最後に試験を受けました。
今回受講させていただいているのは、WSETという教育機関の日本酒講座と試験です。ロンドンに本部を置く世界最大のワインの教育機関です。ワインから始まったこの講座ですが、現在は日本酒のコースがあり、レベル1、3があります。日本酒を発信するアンバサダーとして日本酒の基礎をしっかりと学び、日本酒をご存じない方から何か聞かれた際にも相手に分かりやすくお伝えできるようにという想いで受講しました。
WSET→https://www.wsetglobal.com/jp/japanese-qualifications/
まず、製造工程について学んだ後にテイスティングについて学んだあと、日本酒の楽しみ方や保存方法についても学び、最後にテストを受けるという流れでした。
〈製造工程〉
日本酒の製造工程は発酵、上槽、瓶詰めに分けられます。この過程の間に、「醸造アルコールの添加」や「加水」、「火入れ」が任意で行われます。
1.発酵について
日本酒の原材料は蒸し米、水、麹、酵母です。
まず、酵母を培養するために、主発酵の前に酒母を造ります。酒母が出来上がったら主発酵のためのもろみに移るため、より大きなタンクに酒母・水・蒸米・麹が段階的に投入されます。このタンクに入れる際も、3段仕込みという方法で投入され、酵母以外の菌が入らないようにするための工夫がされています。また、この時タンクの中では「並行複発酵」という日本酒の醸造過程にのみ見られる発酵が行われています。麹に含まれる酵素がデンプンを糖に分解し、その糖を酵母が摂取してアルコールが生成されますが、このように「糖化」と「発酵」が同時に行われるのが「並行複発酵」です。
ワインやビールは単発酵になるため、日本酒の「並行複発酵」は珍しく職人技術が必要な発酵技術であることがわかります。この手法により、日本酒の奥深さは作られています。
2.上槽について
発酵が終わると、次にもろみを「濾す」作業を行います。
全ての日本酒は法律によって製造過程で濾さなければならないと定められていますが、どれぐらいの細かさに濾さなければならないお定められているわけではありません。
ここで粗く濾されている日本酒が「濁り酒」と呼ばれています。
また、上槽する前に任意で「醸造アルコール」をもろみに添加することもあります。醸造アルコールは、濾す際に風味が酒粕側に流れてしまうことを防ぎ、酒側に残す役割があります。
3.瓶詰めについて
最後に、瓶詰めの工程です。上槽された日本酒は、瓶詰めされる前に大抵の場合「加水」をし、約20度のアルコール分が15〜17度に調整します。また瓶詰めされた後劣化臭を防ぐために「火入れ」処理がされますが、この火入れ処理を行わないお酒を「生酒」と呼びます。火入れをしないため、しぼりたてのフレッシュな味わいを楽しむ事ができますが、品質管理に十分注意する必要があります。
以上のような工程を経て、お米とお水から様々な味わいの日本酒が造り上げられます。
日本酒の製造工程は必須工程だけでもこだわりや技術があり、それに加えて任意の工程もあるため、種類や味わいにこれだけの違いがあることを知りました。
〈テイスティング〉
テイスティング入門では、9種類の日本酒のテイスティングをし、味わいについて勉強しました。今までは、「好みの味わいがどうか」というような個々で感じ方が違う説明しかできないという悩みがありました。ですが、今回この講義では、どんな人にも伝わる説明が出来るよう講義いただきました。
テイスティングは、外観、香り、味わいという3つのポイントに着目しながら行います。
まずは外観です。澄んでいるのか、濁っているのか、無色透明か、少し色味があるかなどをグラスを45度傾けて観察します。白い背景だとより正確に確認できるようです。
次に、香りでは、香りの強さ、どんな香りかを確認しました。私が驚いたことは、今まで自分にとって「香りが強い」と感じていたものは実は強いと判断されるものではなかったことです。自分自身の感覚と一般的な感覚の擦り合わせを行うことができたとともに、個人の好みにより感じ方は違うのだろうと思いました。これから説明する際には香りの強さはもちろんどういった香りをそこから感じるかも伝えることでより正確に伝わるのではないかと思いました。
より伝わりやすい香りの表現方法を教えていただいたのですが、「自分の経験に近いものが出てきた場合は、その香りをさらに紐解いて考えてみる」といいそうです。
今までにも、お酒の香りについて「おばあちゃんの家の香りがする」と仰った方がいたようですが、「おばあちゃんの家の香り」はその人にしか分かりません。ですがこれは大きなヒントとなります。「どんな香りがおばあちゃんの家の香り」なのかを分解すると、仏壇のお香の香り、畳の香りなど誰もがイメージしやすい香りの表現が出てくるかと思います。
日常からお花の香りに着目してみたり、フルーツはどんな香りか、熟れてると少し香りは変わるのかなどいつも以上に香りに敏感になって過ごしてみることで、伝えやすい説明が出来ると言うふうに仰っていました。
最後に味わいです。ここでは、甘さ、味わいの強さ、具体的にどんな味わいなのかをポイントにみます。味わいも先程の香り同様、より具体的な表現をすると伝わりやすくなります。個人的には古酒ははちみつやみたらしのようだという表現が1番驚きました。また、酸味の感じ方は飲んでいる際に唾液がよく出るかなども判断基準になると知り、非常に参考になりました。
〈日本酒の楽しみ方〉
日本酒の魅力の一つに、さまざまな温度で楽しめるという点があげられます。今回は、既にテイスティングさせていただいている日本酒から純米酒と純米吟醸酒の2種類をお燗にし、その違いを比較しました。
純米酒は、温度を上げると甘味がぐっと増してお米や穀物の香りもぐんと増します。お酒の角がとれて、柔らかい口当たりになるのも良い点です。続いて純米吟醸酒を試してみると、フルーティーが更に増すと想像したものの逆にフルーティーさが熱さで飛んでしまいました。このことから、種類によって熱燗が適するものとそうで無いものがあり、日本酒の特徴を掴み、その日本酒を引き立てる飲み方をすることが重要だと思いました。
ご講義ではお酒をお料理と組み合わせる上で、お料理と日本酒の風味の強さを同等にする、甘口のお料理には同じ甘味を持つ日本酒を組み合わせる、個人的な好みを尊重することが重要だと仰いました。例えば、私は甘いものに甘いものを合わせるのももちろん好きでしたが、塩辛いものでもいいなと思いました。
また、大変驚いたのが古酒とチョコレートの組み合わせです。古酒のナッツのような香ばしさと旨みがギュッと詰め込まれた濃厚な味わいがチョコレートの甘さと相まって、口の中でアフォガートを食べているかのような素晴らしいマリアージュを感じました。お料理との組み合わせでさらに日本酒を楽しむことができると実感し、こういった魅力も同時に広めていきたいと思いました。
ですが何より重要なことは、感覚は人それぞれであるということです。基本的な知識は大切にしつつ、あまり固定概念に囚われすぎない柔軟さが、日本酒を楽しむ秘訣なのかもしれないと学びました。
〈テスト〉
最後には30問のテストを受けました。合否は2ヶ月先まで分からないとのことですが、結果を楽しみに待ちたいと思います。
◇京都代表 津田朋佳のまとめ
WSET SAKE Level1の講義と試験を受けた体験を通じて、日本酒の製造工程、テイスティング方法、楽しみ方、料理との組み合わせなどについて学びました。製造工程では職人技が沢山あり複雑であるということ、テイスティングでは味わいの表現方法を学べました。
この学びから、京料理には、繊細で上品な飲み口の日本酒が合うのではないでしょうか。京料理は味付けの濃さというよりは、こだわり抜いた出汁を使用し、上品な味わいのものが多く、また京野菜などの素材が味を活かした料理も多いです。そういったところから、日本酒も風味が強すぎるものよりは、あまり強すぎず料理を引き立てるようなものが良いと思います。実際、近畿地方を流れる中硬水により京都の日本酒は飲み口が柔らかいものが多いため、そういった特長が京料理と最高のマリアージュを生むでしょう。今回日本酒の基礎を学ぶことができたのでこれを活かし、京都の日本酒の魅力も伝えられるようになりたいです。