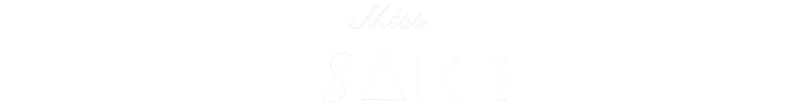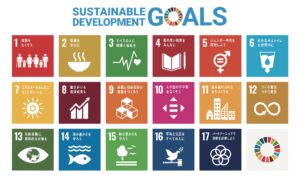皆様、こんにちは。
2021 Miss SAKE 京都代表 森上愛子です。
先日行われた第14回ナデシコプログラムについて綴らせていただきます。
今回は、キャプランワインアカデミー様で「WSET WINE講座 Level1」を受講し、最後に認定試験を受けさせていただきました。
ワインについて本当に基礎的な知識しか持っていなかったため、前もっていただいていたテキストを読んでいる時から驚き、発見の連続で、今回のご講義をとても楽しみにしておりました。
〜学んだこと〜 WSET WINE講座 Level1
ブドウの構成成分とアルコール発酵の仕組み
ワインの原料になるブドウ。
誰でも一度は口にしたことがあるフルーツですが、どの部分にどのような成分があり、味わいは一体どこから生まれてくるのか?とは一度も考えたことがありませんでした。
私の中で「ワイン」というと赤ワインのイメージがとても強く、飲んだ時に感じる特有の渋みの正体は何なんだろう?と思っていたのですが、それは果皮に含まれる「タンニン」という成分でした。
また、アルコール成分のないブドウがどのようにしてアルコール成分を含んだワインになるのか。
ブドウの果肉に含まれる「糖」と、「酵母」を混ぜることにより、アルコール発酵が起こり、「アルコール」と「二酸化炭素」が生まれるとのこと。
ちなみに、ここで発生した二酸化炭素はほとんどの場合、空気中に放出されるそうです。
非常に面白いなと感じたのが、地域によって栽培できるブドウの種類が違うこと、また、同じ品種のブドウであっても、その土地の気候によって味わいが異なるということです!
まず、ブドウの木の育成に最適な地域は、休眠するのに十分な寒い冬が存在する地域です。
ドイツやフランス北部などの冷涼な地域では白ブドウ、オーストラリアやカリフォルニアなどの温暖な地域では黒ブドウを栽培するのが一般的だそうです。
基本的に、気温が低くなるほどブドウの糖分が低くなり酸味は高くなります。
逆に、気温が高くなるほどブドウの糖分は高くなり酸味は低くなり、より円熟した味わいになります。
どの地域で栽培されたブドウなのか、その気候が非常に重要な要素だったのですね!
ワインの醸造方法について
驚きの事実その①
「白ワインと赤ワインは醸造の課程が異なる」
「白ワインは白ブドウだから白、赤ワインは黒ブドウだから赤」となんとも短絡的に考えていた私にとっては大変興味深い事実でした。
白ワインは、①破砕②圧搾③発酵④熟成⑤瓶詰めという課程であるのに対し。
赤ワインは、①破砕②発酵③抜き出し④圧搾⑤熟成⑥瓶詰めという課程になります。
白ワインは、ブドウを破砕して果汁を搾り出す時に「果皮を取り除いてから発酵させる」
赤ワインは、「ブドウ果汁と果皮を一緒に発酵させて」からその後に搾り出す
というのがポイントです。
赤ワインは、果皮を取り除かずに一緒に発酵させているから、赤くなるのですね。
驚きの事実その②
「白ワインを造るのに黒ブドウを使うこともできる」
黒ブドウを使うと色が赤くなるのでは?と思われるかもしれませんが、白ワインは発酵の前に皮を取り除くため、果皮に色があっても、発酵の段階では果肉のみ。
果肉には色がないため、白ワインを造ることが出来るのです!
そして、忘れてはならないのが綺麗なピンク色をした「ロゼワイン」です。なぜあの美しいピンク色のワインが出来るのでしょう?
それは、短時間だけ果皮と接触させた後、果皮を残して果汁を抜き出すからです。
この段階ではわずかにピンク色になっており、果皮なしで発酵が終わります。
ロゼワインの綺麗なピンク色の正体は黒ブドウの果皮の色だったのですね。
ワインのスタイルについて
驚きの事実その③
「ほとんどのワインは辛口である」
甘みはワインの中の糖分によってもたらされるもの。
ほとんどのワインは、アルコール発酵の過程で酵母がブドウの糖を全てアルコールに転化するため、甘みが残りにくいということです。
つまり、甘口のワインを造るためには、非常に多くの糖分が含まれているブドウを使うか、酵母が糖分を全て摂取しきる前に醸造用アルコールを加えて酵母を殺す必要があります。(酒精強化ワインの場合)
辛口ワインがほとんどという事実には、アルコール発酵の仕組みに理由があったのですね。
ワインの味わいについて
日本酒も同じですが、味わいを適切に表現することはとても難しいと感じていたMiss SAKE ファイナリストになってからの日々。
しっかりとそのお酒の魅力を人に伝えるには、学術的な学びから得た知識が必要だったのだと今回の講義を通して気がつきました。
ワインの場合は、味わいを表現する際には「甘み」「酸味」「渋み」「ボディ」などを味わいの中から見いだしていくことになります。
また、「香り」も非常に大切な要素であることがわかりました。
ワインの香りと風味は、ブドウ自体からもたらされるものもあれば、醸造や熟成過程でもたらされるものもあります。
ほとんどのワインは果実の風味があるとのこと。
例えば、冷涼な気候で栽培されたシャルドネにはリンゴやレモンなどの風味が、温暖な気候で栽培したシャルドネにはモモやパイナップルなどの風味が感じられます。
そして発酵や熟成にオーク樽が使用された場合は、スギやグローヴ、ココナッツ、ヴァニラなどの風味が加わるそうです。
ブドウの品種に加え、発酵や熟成過程でも香りが変化します。
このことから、非常に多様なスタイルのワインが存在していることがうかがえます。
テイスティング
さて、学術的な知識を得たところで、実際に9種類のワインをいただきながら「外観」「香り」「味覚」を表現してみました。
驚きの事実その④
「同じ色のワインでも味わいが実に様々!」
知識としては自宅で学んでいたため少しは理解していたつもりでしたが、実際にいただいてみると、その香りや味わいの多様さに驚き、とても興味がわきました。
冷涼な地域ならではのレモンやリンゴの味わいや、温暖な地域ならではのモモやパイナップルの味わいなどをしっかり感じとることが出来ました。
驚きの事実その⑤
「ワインから石油の香りが…?」
この日にいただいた白ワインの中で私が一番美味しいなと感じた「ヴェレナー ゾンネンウアー リースリング シュペートレーゼ」
白い花の華やかな香りに、モモやパイナップルのフルーティーな味わい、その中にふんわりとですが石油の香りがあることに大変驚きました!
この石油の香り。「ペトロール香」というそうです。
ブドウからできたワインから石油のような香りがするなんて、衝撃的ですよね。
でもそれがとっても美味しいのです。
このペトロール香は、熟成する過程で発生する香りだそうです。
どのような容器で熟成されるかというのも、ワインの個性を生み出すのにとても重要なのだということが理解できました。
料理との組み合わせ
今回のご講義では、
・塩(塩味) ・レモン汁(酸味) ・味の素(旨み) ・クッキー(甘み) ・イチミトウガラシ(辛み) ・コンテチーズ(旨み+塩味)
この6種類の食べ物とのペアリングを試しました。
料理に合うワインを選ぶのに大切なことは、個人の嗜好が最も重要だとのこと。
しかし、負の影響を及ぼしてしまう組み合わせがいくつかありました。
驚きの事実その⑥
「甘みと旨みのある食べ物には要注意!」
それぞれのワインをクッキー、味の素を合わせてみると…
美味しいワインだったはずか、ものすごく渋いと感じたり、ものすごく酸っぱいと感じたり、まろやかなフルーティーさが全く感じられなかったり。
こんなにもワインの味わいが変わってしまうのかと、声を上げてしまうほど衝撃を受けました。
逆に、塩とレモン汁は渋みや酸味をやわらげたり、フルーティーな味わいがより一層円熟したものに感じられたり、総合的に相性が良いと感じました。
旨みのある食べ物には要注意。
最後に試したコンテチーズですが、チーズにも旨みはありますよね。
実際に試してみると…
どの食べ物ともとっても相性が良く、ワインの味わいを存分に楽しむことが出来ました!
チーズは旨みの中に塩味があるため、美味しくいただけるのだそう。
ワインのお供には最高の組み合わせだと感じました!!
ご講義の前には、料理との組み合わせがとても難しそう…と思っていましたが、基礎的な知識を得た上で、実際に香りを感じ、味わうことにより、体感としてワインへの理解を深められてように感じ大変嬉しく思っております。
「知る」ことで終わらずに「伝える」「勧める」ことが出来るよう、さらに知識を深め、色々な種類のワインを自宅でもいただこうと思っております。
多様で奥深いワインの世界を堪能させていただくことができた、貴重な学びの場となりました。
キャプラン株式会社 オースタン紗知子様、貴重なご講義を誠にありがとうございました。
※テイスティングと撮影時のみマスクを外しております。